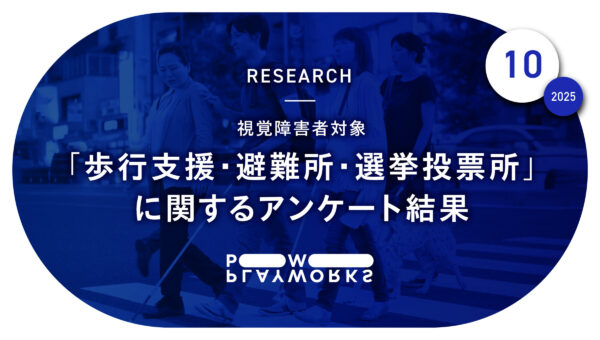PLAYWORKS INTERN INTERVIEW 11|小島 千佳

PLAYWORKSのインターンは、クライアントワークやプロジェクトに関わる中で、インクルーシブデザイン・サービスデザイン・ワークショップデザインについて学んでいます。今回は2024年4月からインターンとして活動している、小島千佳のインタビューをお送りします!
小島 千佳 OJIMA CHIKA
専門学校桑沢デザイン研究所 夜間部ビジュアルデザイン専攻 1年
神奈川県横浜市出身。聴覚障害の父親との体験から福祉に興味を持ち、高校1年生で参加した「ダイアログ・イン・サイレンス」をきっかけにインクルーシブデザインと出会う。昭和女子大学で社会科学を学んだ後、「作り手としてデザインに関わりたい」という想いから、大学3年生時にダブルスクールで桑沢デザイン研究所に通学。2025年4月より同校夜間部でグラフィックデザインを本格的に学ぶ。趣味は美術館・動物園・水族館巡り。「気になることがあったら、必ずその場所に行って学ぶ」ことを心がけている。

左:小島千佳 右:インタビュアー 大崎博之
まずは小島さんのことを簡単に教えてください
私は現在、桑沢デザイン研究所の夜間部でグラフィックデザインを学んでいます。私がインクルーシブデザインに興味を持ったのは、高校1年生の体験がきっかけです。
父が聴覚障害者だったこともあり、「ダイアログ・イン・サイレンス」という、声を使わずにボディランゲージだけでコミュニケーションをおこなうイベントに参加したんです。私をアテンドをしてくれた方がユニバーサルデザイナーとして活躍されていて、初めて「ユニバーサルデザイン」という概念を知りました。
幼少期から絵を描くことやモノづくりが大好きだった私にとって、「大好きなデザインが、父親とも関係する福祉に役立てる」と知り、今でも鮮明に思い出せるくらいに感動したんです。

「ダイアログ・イン・サイレンス」を体験した様子
でも同時に、「父と通じ合えていた」と思っていたコミュニケーションが、思っていた程ではなかったのかもしれない —— そんな疑問も芽生えました。私は手話ができないので、父とは読唇術で意思疎通を図るのですが、その状態で本当にちゃんとコミュニケーションが取れているのだろうか、と。
そうした疑問から、もっと多くの人が過ごしやすい社会とは何かを考えるようになり、大学では「社会の仕組みを見直し、そこからデザインを考えたい」と思い、現代教養学科を専攻。卒業論文では、聴覚障害者が陥りやすい「情報障害」について研究しました。なかでも、家族の会話に置き去りにされがちな「ディナーテーブル症候群」を中心に調査を進めました。
でも大学で学んでいくうちに、「やっぱり自分は作り手としてデザインに関わりたい」という意識がどんどん強くなっていったんです。実際、インクルーシブデザインに関わっている人は、デザイン分野の出身者が多く、「自分がやりたいことは、モノを作れる人じゃないと実現できないな」と感じるようになりました。
そんな思いをきっかけに、大学3年生のときにダブルスクールで今の専門学校に通い始め、大学卒業後も就職ではなく、桑沢デザイン研究所の夜間部でデザインの勉強を続ける道を選び、今に至ります。


大学時代の活動の様子
PLAYWORKSでインターンをはじめたきっかけは?
大学1年生のとき、インクルーシブファッションをやられている会社で長期インターンをしていたのですが、それがきっかけでPLAYWORKSの存在を知りました。私にとっては、専門学校で得たデザインの知識を実践的に習得する機会がほしいと思っていたタイミングで、日本のインクルーシブデザインの最前線で活躍しているPLAYWORKSに出会ったことになります。
特に惹かれたのは、当事者と一緒にモノを作っていく「ともに作るプロセス」を大切に実践されているところです。PLAYWORKSであれば、インクルーシブデザインのプロセスや当事者とのワークショップなど、現場から学ぶことができると思い、応募を決めました。
PLAYWORKSでは具体的に何をしているのですか?
週1回のオンライン定例ミーティングを基本に、ワークショップのアシスタントや展示会の説明員、YouTubeの動画編集など、幅広く関わっています。私は気になることは必ず現場に行って学びたいと思っているので、インターンの活動にはできるだけ手を挙げるようにしています。稼働率はインターン生の中で一番多いと思います。
PLAYWORKSは全国にクライアントがいますが、なかでも東京は多いので、月に2〜3回のペースでワークショップやイベントに関わっています。さまざまな企業のインクルーシブデザインのプロジェクトを間近で見られるため、貴重な学びの機会になっています。
最近参加したのは、高島屋の「Fashion for ALL your SENSES」というプロジェクトです。視覚障害者のファッションに関するリサーチから、ワークショップでのアイディエーション、プロトタイプによるユーザーテスト、店頭や什器のデザイン、WEBサイトのアクセシビリティ、販売員の接客研修まで、すべてのプロセスに参加させていただきました。
そのほか、デザインカンファレンス「Designship 2024」での活動も記憶に新しいです。


「展示会」で説明員をおこなう様子
PLAYWORKSで印象に残っている活動や出来事は?
特に印象に残っているのは、「ガイドヘルパー育成研修」です。この研修では受講生としてガイドヘルパーになるためのトレーニングを受けたのですが、私はもともと聴覚障害への関心が強かったため、視覚障害の方との接し方は右も左もわからない状態で、当日はとても苦戦しました。
研修で学んだことは、ガイドヘルパーは「利用者さんの目になる仕事」だということ。実際にやってみると、安全な案内と楽しい会話を両立させるのがとても大変で… 目的地のルートを確認し、危険な箇所を伝えながら、景色などの情報も言葉で伝える。意識を向ける範囲がとても広く、言葉選びにも気を抜けない緊張感がありました。
でも、人の話を聞くのが大好きな私にとって、当事者の方と直接お話できることは、家で勉強するよりもたくさんのことを吸収できる気がして、嬉しかったですね。今では正式にガイドヘルパーとしての登録もして、プライベートでも同行援護をおこなっています。


「ガイドヘルパー育成研修」でトレーニングを受ける様子
インターンを通して得られたことは何ですか?
一番得られたと感じるのは、たくさんの当事者と出会って話した経験です。特に、当事者の視座を得られたのはとてもありがたかったです。
また、家族との関わり方も大きく変わりました。今まで父親がもっとも近い障害当事者だったのですが、家族以外の当事者と話す機会が増えたことで、家族とのコミュニケーションの取り方にも変化がありました。もっと聴覚障害者とのコミュニケーションについて考えたいと思うようになり、5月から手話奉仕員の養成講座に通いはじめています。
これまで自分の興味のあるインクルーシブデザインや福祉に「どのように関わったら良いのかわからない」という感覚がありましたが、インターンでの経験を通じて、「モノづくりを通じて社会にイノベーションを起こしたい」という、進むべき方向が明確になったのが何より嬉しかったです。
PLAYWORKSはどんな会社ですか?
インクルーシブデザインという正解がなく難しい領域において、「ビジネスとして新たな価値を社会に実装していく力がある会社」だと思います。私が参加した高島屋のプロジェクトでも、丁寧なデザインリサーチから徹底的にこだわるモノづくり、販売員の接客まで、すべてのプロセスがとても濃密でした。当事者や社会が本当に求めるアウトプットを形にするプロジェクトが、継続的に行われています。
PLAYWORKSの特徴は、何よりも「ともにつくる」を大切にしているところ。ワークショップに参加している誰もが生き生きとして、アイデアやプロダクトが生まれる瞬間に立ち会えます。それは私にとって、何よりもの喜びです。
全国から多様な分野で学ぶ学生インターンが揃っていて、発達障害やジェンダー、プロダクト、サービス、ファッションなどさまざまな領域に関心を持つメンバーが集まっているため、新しい情報や刺激が得られる場所になっています。
これから挑戦したいことは何ですか?
現在はデザイナーになるために勉強しているので、PLAYWORKSで得たものを活かして、当事者と共創するモノづくりをしていきたいです。特に関心があるのは教育分野です。PLAYWORKSのインターンを始めてから、発達障害や学習障害がある子どもたちと出会う機会も増えて、関連するプロジェクトやリサーチに関わる機会もありました。
今は、発達障害の子どもたちが外出や学校生活を楽しめるようなプロダクトを、自主的に制作しています。一番得意としているグラフィックデザインと、やりたい分野が合致する部分なので、当事者の方と一緒に完成させていきたいです。PLAYWORKSで学んだ「ともにつくる」体験を、自分の制作にも活かしていきたいですね。
未来のPLAYWORKSインターン生に対してメッセージをどうぞ!
デザインを学ぶ学生以外にも、さまざまな領域を学んでいるインターン生が増えており、広い学問分野のバックグラウンドを持つ同年代と繋がる機会は、ここしかないと思います。
インターンに応募する際、学業との両立に不安を感じる人も多いかもしれません。私自身も最初は不安でしたが、代表のタキザワさんが調整してくださり、自分のライフスタイルに合わせて柔軟に活動ができています。
私がインターンを経てお伝えしたいのは、「100回の授業よりも、1回のPLAYWORKSの現場の方が、たくさんの出会いと発見がある」ということです。学校では理論を体系的に学ぶことができるし、知識もたくさん増えますが、机上の空論のこともある。実際にPLAYWORKSの現場で当事者とお話をすると、想像していたのとは全く異なる反応があったり、その人のしぐさや行動から多くの発見があることに気づかされます。
人と会ったり話したりすることで、学校で勉強するよりもたくさんのことを吸収できるんです。ぜひ一緒に現場にしかない発見に、出会いに行きましょう!
PLAYWORKS INTERN INTERVIEW 10|岩下 恵都
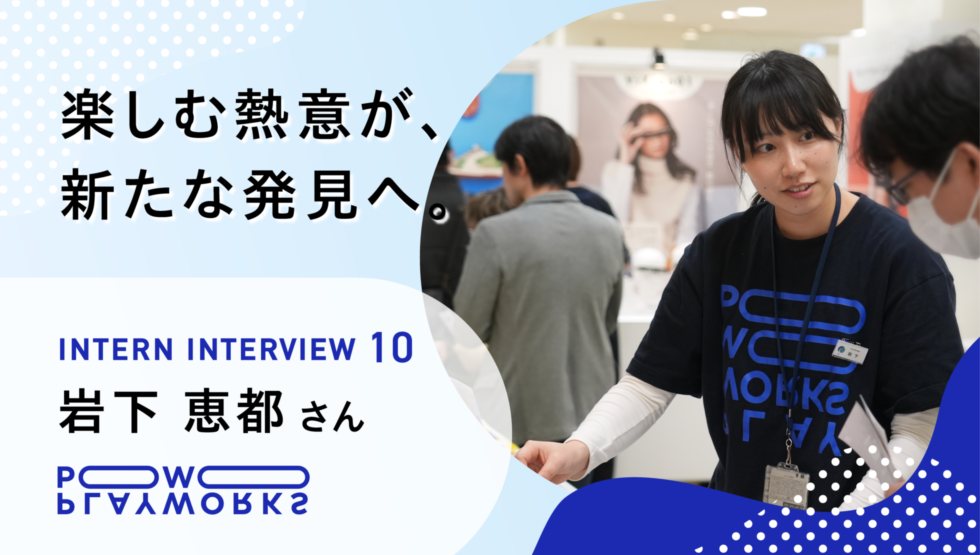
https://playworks-inclusivedesign.com/column/column-9264/