PLAYWORKS INTERN INTERVIEW 10|岩下 恵都
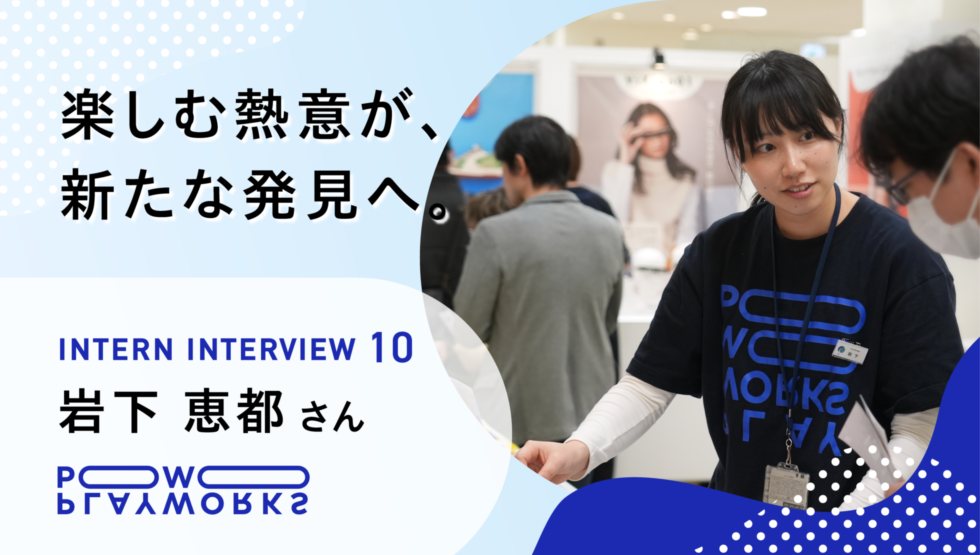
PLAYWORKSのインターンは、クライアントワークやプロジェクトに関わる中で、インクルーシブデザイン・サービスデザイン・ワークショップデザインについて学んでいます。今回は2023年10月からインターンとして活動している、岩下恵都のインタビューをお送りします!
岩下 恵都 IWASHITA KEITO
九州大学大学院 芸術工学府 芸術工学専攻 ストラテジックデザインコース 2年
福岡在住。大学では工業設計学科でプロダクトデザインを学んだ後、現在は大学院に進み、サービスデザインやインクルーシブデザインについての調査から実装までを包括的に行っている。趣味は小学校の頃から続けているバスケットボール。アイデアに悩んだときやリフレッシュしたいときは、体を動かすことで気分転換している。

左:インタビュアー 目次ほたる 右:岩下恵都
まずは岩下さんのことを簡単に教えてください
私は現在、九州大学大学院のストラテジックデザインコースで、サービスデザインやインクルーシブデザインについて学んでいます。私がデザインに興味を持ったきっかけは、小学5年生のときに「Dr.Grip」というシャーペンに出会ったことでした。
もともと文房具が大好きだったのですが、「Dr.Grip」は医師が大量の文字を書く銀行員や速記者が腱鞘炎になるのを防ぐために開発した商品だと知り、ますます大好きになったんです。実際に自分でも使ってみると手指への負担が少なく、勉強の時間が快適に変わったことに感動して、「自分も誰かの生活を良くするものを作りたい」と思うようになりました。
そんな原体験を経て、大学では工業設計学科でプロダクトデザインを学ぶことにしました。学んでいくうちに「物をどうやって市場に出していくか」「どういうものが必要か」といった市場調査の側面により興味を持ち、現在のストラテジックデザインコースへ通うようになりました。
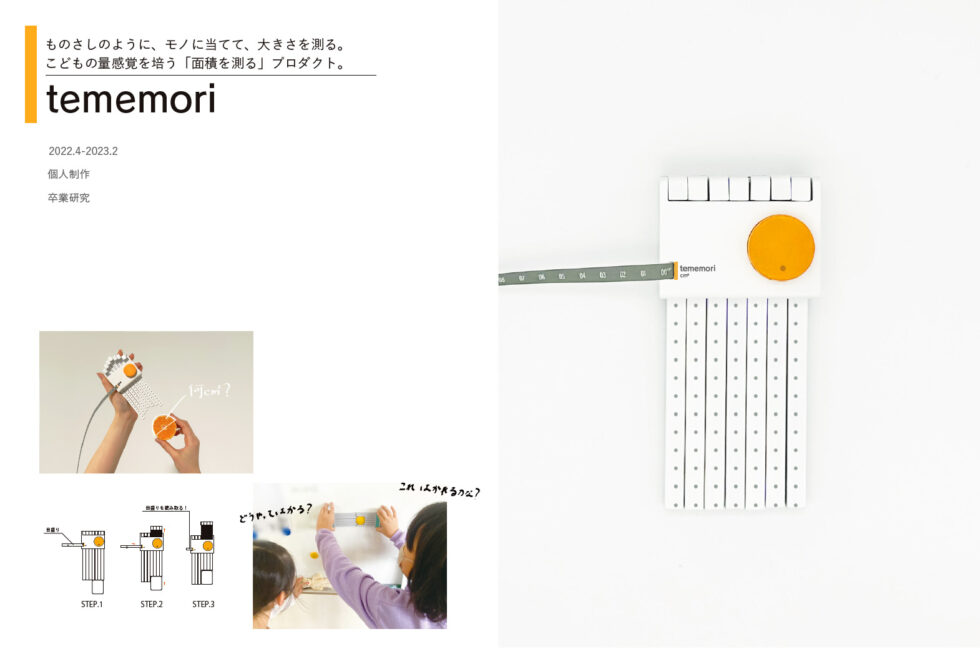
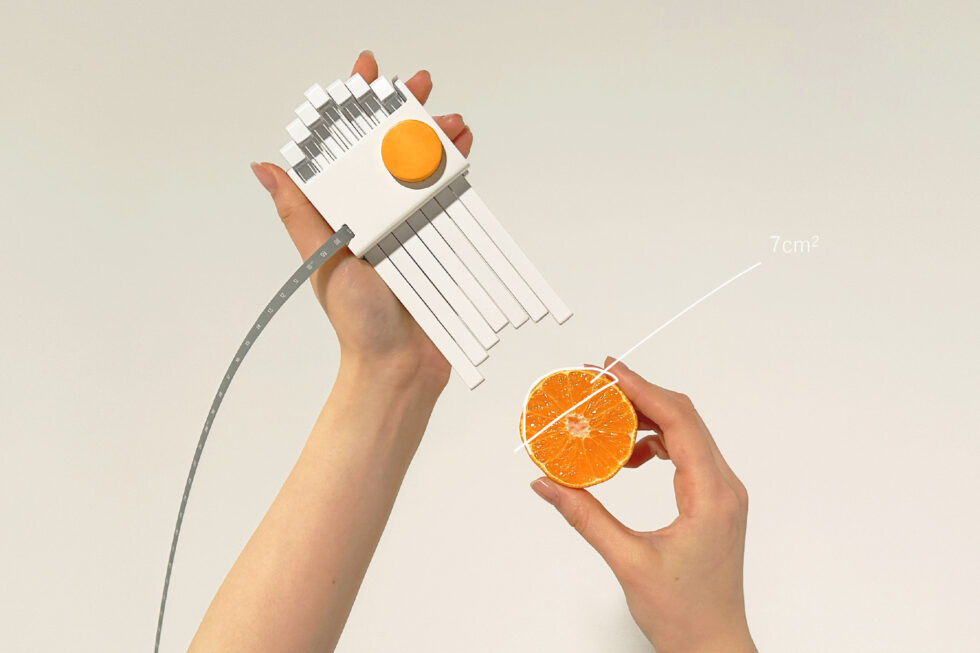
講義では、グループワークを通じて実践的なプロジェクトに取り組む機会が多く、みんなで議論しながらアイデアを練っていくプロセスがとても楽しいです。私が取り組んだなかでも特に印象深かったのは、九州大学と病院が連携して取り組んだプロジェクトです。バングラデシュの妊婦さんのために「オンライン検診アプリ」の開発をしました。
5日間バングラデシュに現地滞在をして、都市部から車で6〜7時間かけて農村地域まで赴き、妊婦の方々へのインタビューを実施しました。この調査を通じて、バングラデシュでは「怨念によって流産をする」という言い伝えがあり、妊娠を隣人に知られたくないと考える文化的背景があることや、長時間の移動による身体的負担など、日本では気づけない課題を発見することができました。


PLAYWORKSでインターンをはじめたきっかけは?
インクルーシブデザインに興味を持ったのは、大学で平井康之教授の講義を受けたことがきっかけでした。日本にインクルーシブデザインを広めた第一人者とされる平井教授は、「リードユーザーに寄り添い、その本当の思いやアスピレーション(願望)に基づいてデザインを考えていく」というプロセスを大切にされています。その考え方に共感し、私もインクルーシブデザインに携わりたいと思うようになりました。
その後、大学でタキザワさんの講義を聞く機会が二度ありました。学生のアイデアにタキザワさんが講評する機会があったのですが、ビジネスでインクルーシブデザインを実践されているからこその、具体的で鋭い指摘に驚きました。
それまでインターンの経験はなかったのですが、PLAYWORKSでインターンを募集していることを知って、「ここでより深く実践的にインクルーシブデザインを学びたい」と思い、参加を決めました。
PLAYWORKSでは具体的に何をしているのですか?
普段は福岡で暮らしているため、毎週のオンライン定例ミーティングに参加して、現在進行中のインクルーシブデザインプロジェクトについて、ビジネスの観点も含めて深く学ばせてもらっています。
また、東京に行った際や福岡でワークショップなどが開催される時は、アシスタントを担当させてもらうこともあります。福岡に暮らしているので、関東のプロジェクトに参加できる機会は少ないのですが、参加できるチャンスがあれば必ず参加しています。
そのほかにも、PLAYWORKSのYouTubeチャンネルの動画編集や、大丸福岡天神店での企画展「インクルーシブデザインでつながる未来 」では、説明員を担当しました。


日々の取り組み以外にも、ほかのインターン生と協働してデザインコンペに参加したこともあります。聴覚障害のある方へのインタビューを通じて、学校のグループワークにおける課題解決の提案も行いました。
PLAYWORKSで印象に残っている活動や出来事は?
どの活動も印象に残っていますが、特に大手家電メーカーとのプロジェクトは、とても多くの学びがありました。PLAYWORKSが実践しているインクルーシブデザインのメソッドをもとに、より応用性の高いプログラムとしてデザインし直す試みで、メーカーの社員や視覚障害・聴覚障害リードユーザーの皆さんと一緒にさまざまな手法を体験し、体系的に学べる貴重な機会となりました。
また、博多大丸さんと実施した「聴覚障害者とのお買い物ワークショップ」にアシスタントとして参加した際は、アイスブレイクの手法に驚きました。ワークショップは、聴覚障害リードユーザーの方々が買い物をする様子を観察し、博多大丸で使用する「指差しコミュニケーションパンフレット」を制作するというもの。
最初は緊張感のあった現場でしたが、タキザワさんのアイスブレイクによって徐々に打ち解けて、最後にはその場の全員が積極的に意見を出し合える雰囲気になっていく様子にびっくりしたんです。タキザワさんのファシリテーションや空気づくりを見て、私も同じようなワークショップをデザインできるようになりたいです。
ワークショップ後にはプログラムデザインやワークの意図などを、直接タキザワさんから解説してもらえるので、実践に基づいたワークショップに触れられることが嬉しいです。

インターンを通して得られたことは何ですか?
デザインに対して熱意を持つことの重要性を知ったことですね。タキザワさんやインターン生と食事をする機会があるのですが、そこでタキザワさんのこれまでの社会人としての歩みや、デザイナーとして大切にしていることなどを教えてもらいました。
お話を聞いていると、ビジネスとしてインクルーシブデザインに取り組む難しさがありつつも、自分自身が楽しむことが熱意に繋がっていると実感しました。その熱意があるからこそ、リードユーザーの思いを汲み取って形にするところまで走り切れる。それがわかったことは大きな発見です。
また、大学院で学ぶデザインと実務の間には大きな差があることも実感しました。大学では「物を作るまで」の過程は経験できますが、それをビジネスとして実装していくには、もう一段高い視点と熱意、そして責任感が必要だと学びました。
PLAYWORKSはどんな会社ですか?
インクルーシブデザインを実践的に学べる、貴重な機会に溢れた会社だと思います。ビジネスとしてインクルーシブデザインを展開していく現場を、間近で見ることができるのが一番の魅力です。例えば、指差しコミュニケーションパンフレットのプロジェクトでは、クライアントへの提案や広報、販売価格など、学生ではなかなか経験できないリアルな話に触れることができました。
また、PLAYWORKSが実践するインクルーシブデザインの特徴は、リードユーザーと一緒にデザインを作っていくアプローチにあります。リードユーザーの皆さんと一緒に体験したり、対話をするプロセスを通じて、「本当に必要とされるもの、新しい価値」を見つけていく体験がとても魅力的です。
これから挑戦したいことは何ですか?
来年から社会人になるので、PLAYWORKSで学んだことを活かして新たな挑戦をしていきたいです。特に自分でワークショップを実施してみたいという思いが強くなりました。就職先ではワークショップをおこなう機会があるので、アシスタントとして経験を積みながら、自分ひとりでワークショップのデザインやファシリテーションをおこなえるようになりたいです。
PLAYWORKSのワークショップでは、アイスブレイクで参加者の緊張をほぐしていくプロセス、プログラムの組み立て方など、綿密に計算された工夫がたくさんありました。そういった「アイデアを引き出す技術」を学び、実践していけたらPLAYWORKSでの経験がより活かせるんじゃないかと考えています。
何よりどんな場面でも大切にしたいのは、タキザワさんから学んだ「物事に熱意を持って取り組む姿勢」です。やってみないとわからない大変さもありますが、楽しみながら取り組むことが熱意につながり、それが良い結果を生み出すという循環を、自分の仕事でも作っていきたいです。
未来のPLAYWORKSインターン生に対してメッセージをどうぞ!
PLAYWORKSには、私のように東京以外に暮らしていても充実した活動ができる環境があります。私自身、最初は九州在住でインターンにちゃんと参加できるか不安でしたが、定例のミーティングは完全オンラインで実施されているため、遠方にいても疎外感なく参加できています。
また、学んでいることや志が近いインターン生が集まっているので、一緒に話すだけでも刺激になるはずです。関東でのプロジェクトにも機会を見つけて参加することもできますし、地方でもワークショップや展示会が開催されることもあり、どこで暮らしていたとしても十分な学びが得られます。
リードユーザーと一緒にアイデアを考え、形にしていく経験は本当に貴重なので、インクルーシブデザインに興味がある方はぜひチャレンジしてみてください!
PLAYWORKS INTERN INTERVIEW 09|竹田 遥
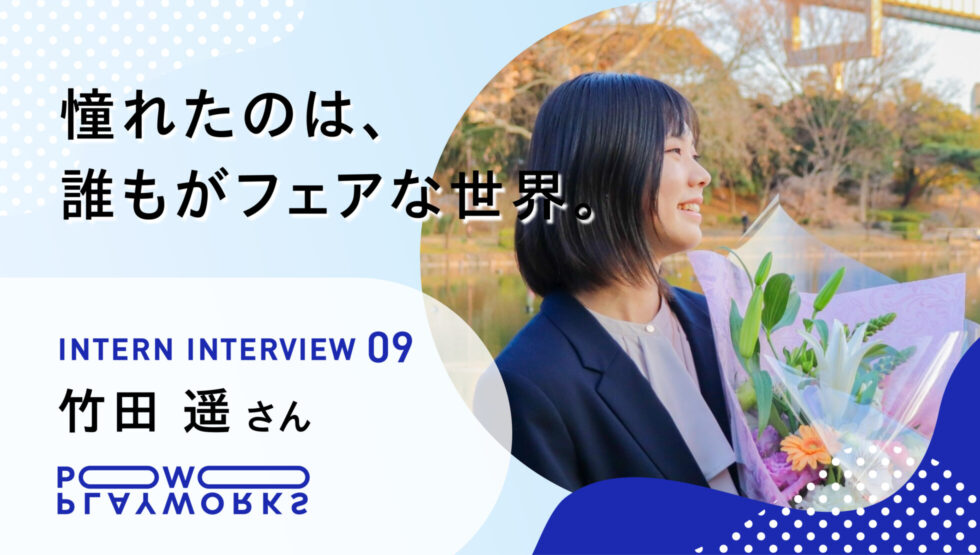
https://playworks-inclusivedesign.com/column/column-7554/




